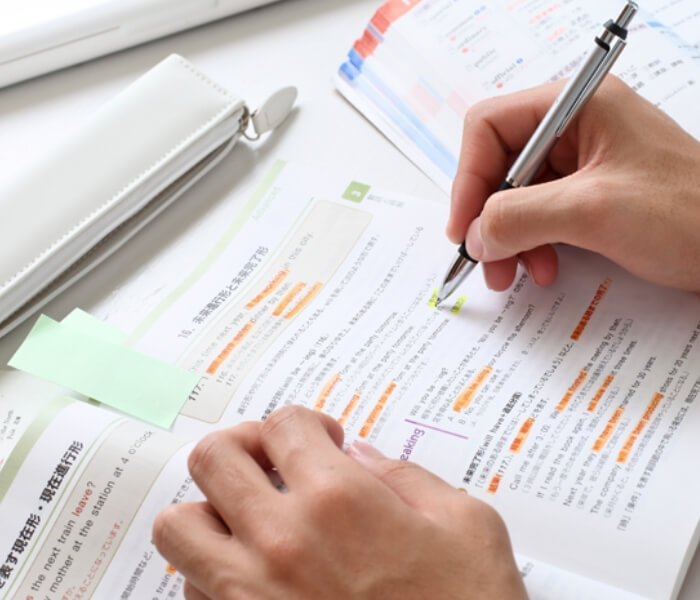-
A.
注意点として、
・実務研修(※)は一定の場合を除き認められてないこと
・研修期間は通常1年が想定されること
があげられます。
実務研修と非実務研修の違いに関しては、
非常に分かりづらい部分のため、下記ご参照ください。
目次のサンプル
目次
●実務研修/非実務研修
1 実務研修の禁止(公的機関を除く)
在留資格「研修」では、原則として実務研修は認められていません。
下記の場合のような、公的機関の事業として行われる研修である場合にのみ、実務研修が認められます。
【公的機関】
・国若しくは地方公共団体(※1)の機関又は独立行政法人
※1 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団をいう。
・独立行政法人国際観光振興機構
・独立行政法人国際協力機構
・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センター
・国際機関
・特殊法人(※2)
※2 日本私立学校振興・共済事業団、株式会社日本政策金融金庫、日本中央競馬会、日本放送協会 等
・その他、研修事業の運営費用の主たる部分(50%以上)を国、地方公共団体、特殊法人又は独立行政法人が負担している場合
2 実務研修と非実務研修の違い
研修内容が実務研修にあたるかどうかは、
・講義形式か否か
で決まるわけではなく、
・研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否か
により決定されます。
上陸基準上、「実務研修」については、商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修のほか、商品の生産をする業務に係るものにあっては、商品の生産をする場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものでない、生産機器の操作に係る実習も含まれる旨定められている。
すなわち、一般の職員と同様に生産ラインに参加し、商品を生産することを通じて技能等を修得する場合などがこれに当たる。
また、「実務研修」か否かは講義形式か否かにより決まるものではなく、研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否かにより決定する。
(省略)
ただし、「生産機器の操作に係る実習」を行う場合でも、工場の敷地内にある別棟の研修センターや商品生産施設内であっても商品を生産する区域とは明確な区分がされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して試作品(研修生以外の者が若干の点検、仕上げを行うことによって最終的に商品となるものは含まない。)を製造する場合や、通常の商品を生産するラインであっても、あらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用することが第三者にも明確に分かる状態である場合には、「非実務研修」として取り扱う。
<引用元:在留審査要領 24節の2 「研修」>
●研修期間
また、「研修」には、2年・1年・6月・3月の在留期間が定められていますが、
原則として1年までの在留とされています。
1年を超える研修を実施することに合理的理由があるものについては、2年までとされています。

サポート満足度 97%※2024年 自社調べ
お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。
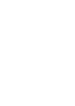
初心者の方でもご安心ください
システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。
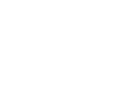
導入支援サービス(有償)
導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。
導入社数
2,000社
※2025年2月時点
事務対応時間
55%削減
対応可能言語数
24言語
SERVICES
外国人労働者の採用から帰国まで、すべてをカバーするトータルサポート